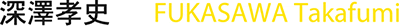TITLE:家族の客体 Object of Family
YEAR: 2017
本郷新記念札幌彫刻美術館 展覧会「家族の肖像」出展
<テキスト>
家族の客体
民俗学的な視点を用いて自分の家族の客体化を試みようと思う。家族の客体化とは、自分たちの土台となってきた歴史や風俗、近代化を経た現代を生きているということなども踏まえた上の家族の新たな年中行事を考えてみることに近いのかもしれない。
今回、その試みとして、僕たちは丸石神を砂糖で作った。丸石神については後で記述するが、その多くは現在僕の出身地の山梨県に道祖神として祀られている。制作物は結果としては大きなみたらし団子みたいなものができた。なるべく家にあるもの、身近な素材でできること、みんなでできることを念頭に置いて制作した。僕らの生活に脈々と続いてきた背景全体の可能性がバラバラのまま交差して、観念化されるような何かを目指した。
僕の父方の祖父と祖母の墓は、山梨県大月市の山の上にある。おそらく近くで拾ってきたのだろう、漬物石くらいの大きさの石だった。僕の父が亡くなる前によくある直方体の墓石を建てて立派になったが、僕も含めた家族はその石も大事に思っていて一緒に祀ってある。石は二つあったのだが、誰かが手頃なサイズだと思ったのか、新しい墓を建てて数年経った頃に一つなくなってしまった。僕にとって墓は、角の取れて楕円がかったちょうどいいサイズの石だった。完全な丸石ではないが、それが僕にとっての最初の石の神様だったと思う。
山梨県には全県にわたって広く道祖神が祀られている。中沢厚『石にやどるもの 甲斐の石神と石仏』によると、道祖神とは、日本全土に広がっていたようだが、今では全県的には山梨と長野だけになった。あとは部分的に新潟や神奈川などでも続いている。道祖神は簡単にいうと村の魔除けの神のようなものだ。陽石と言って男性の陰部の形をしたものが多く、それが転じて、江戸時代には、男女二神が彫られた道祖神が多く作られるようになる。起源はわからないが、700年代に編纂された日本書紀にはすでにサイノカミ、クナドノカミという道祖神と性格を同じにした神の存在が記述されており、時を同じくして中国からも旅人のための道祖という神が導入されている。天尊降臨、天照大神の道案内役であるため猿田彦の附会も見られる(附会とはこじつけのこと)。仏教伝来後は地蔵や馬頭観音とも習合するなど、道祖神は様々な神が混じり合い時代を超えて現在に続いているようである。民俗学者の中沢厚は、時代ごとの政治と結びつき統治の道具立てとなっていた神社や寺院とは異なり、現在まで古代性を失わず残っているのは濃厚な民族信仰だったにほかあるまいと述べている。
道祖神の中でも丸石道祖神というものがあってこれはほとんど山梨にしか存在しない。ただの丸い石が立派な土台や、木や石の祠などに置かれているのだ。山梨以外にはほとんどないが、山梨全土には700箇所以上今も祀られている。中沢厚は、丸石道祖神の起源を縄文時代ではないかと推論している。丸石とともに縄文時代に作られた石棒も祀られているからだ。ただ石棒よりも、丸石の方が分布域が圧倒的に広いことから、より古い時代から引き継がれた信仰かもしれないと考えている。また、山梨の丸石の生成過程として川に流されて丸くなった説に違和を感じ、中米コスタリカの山林中の丸石群を研究していたアメリカの学者スターリングの研究を引用し、火山灰の深部にできた結晶が表出したものではないかという仮説も立てている。
近代人が道祖神をもう一度見つけたのは、柳田國男から始まった一国民俗学という視点からである。佐谷眞木人著『民俗学・台湾・国際連盟 柳田國男と新渡戸稲造』によると、日本の民俗学は明治の近代化政策から始まった。台湾を植民地化することで、近代的な主体である日本の客体として台湾をみなしていったのである。そして植民地主義の一手段として民俗学は生まれた。土俗的な暮らしを行う先住民族である彼らを人類学の対象として調査することで私たちの民俗学は始まったのだ。その後、柳田國男によって文化相対主義への反省から、自らを対象化していく一国民俗学が生まれた。
柳田國男は新渡戸稲造の直系とも言える存在だった。新渡戸稲造は札幌農学校で農政学を修め、後藤新平に呼ばれ明治34年1901年に技師として台湾総督府に勤務する。当時の台湾には北海道開拓の経験を植民地化に活かすため、札幌農学校から多くの人材が送られたらしい。新渡戸は現地を視察し、砂糖の可能性に目をつけ、多くの製糖工場を整備し、日本と台湾の近代化に大きく貢献をした。日本と台湾にとって製糖工場は近代化のまさに象徴だった。台湾の国の特性を尊重する人権的な視点ではなく、あくまで効率的な視点で台湾独自の政策を考えていく分離主義的な視点から生まれたものだった。民俗学の萌芽は、それぞれの民族の独自性を尊重する視点とは全く逆の視点から生まれたものだった。
家族を一つの主体と考えた時に、可能な芸術表現は何かと考えたときに、「過去に育つこども」を産むことなのではないかと僕は考えた。丸石神の特性には、数千年の時を越えて、時代ごとに様々な名前の神様として呼ばれ続けてきたが、路肩で雨ざらしに置かれているにも関わらず一貫して、特異な物質以上の何かとして祀られてきたということだ。単なる丸い抽象的な物体ではあるが、近代芸術を超えた普遍性が備わっていると言えると思う。妻の出身在住地ということが理由で、私たちは現在(2017年)札幌市に住んでいる。双方の民俗学的視点で浮かび上がらせた背景を結びつける行為は、もう一つの結婚と言えるかもしれない。そこから生み出されたものが、家族の客体であり、「過去に育つこども」のことである。私たちの生活を多層化させ、未来へ向かう私たちのこどもに、全く逆に向かう何かを出会わせること。その出会いを創造する態度が家族の芸術であると考えたい。
参考文献
中沢厚『石にやどるもの 甲斐の石神と石仏』(平凡社、1988年)
佐谷眞木人著『民俗学・台湾・国際連盟 柳田國男と新渡戸稲造』(講談社、2015年)